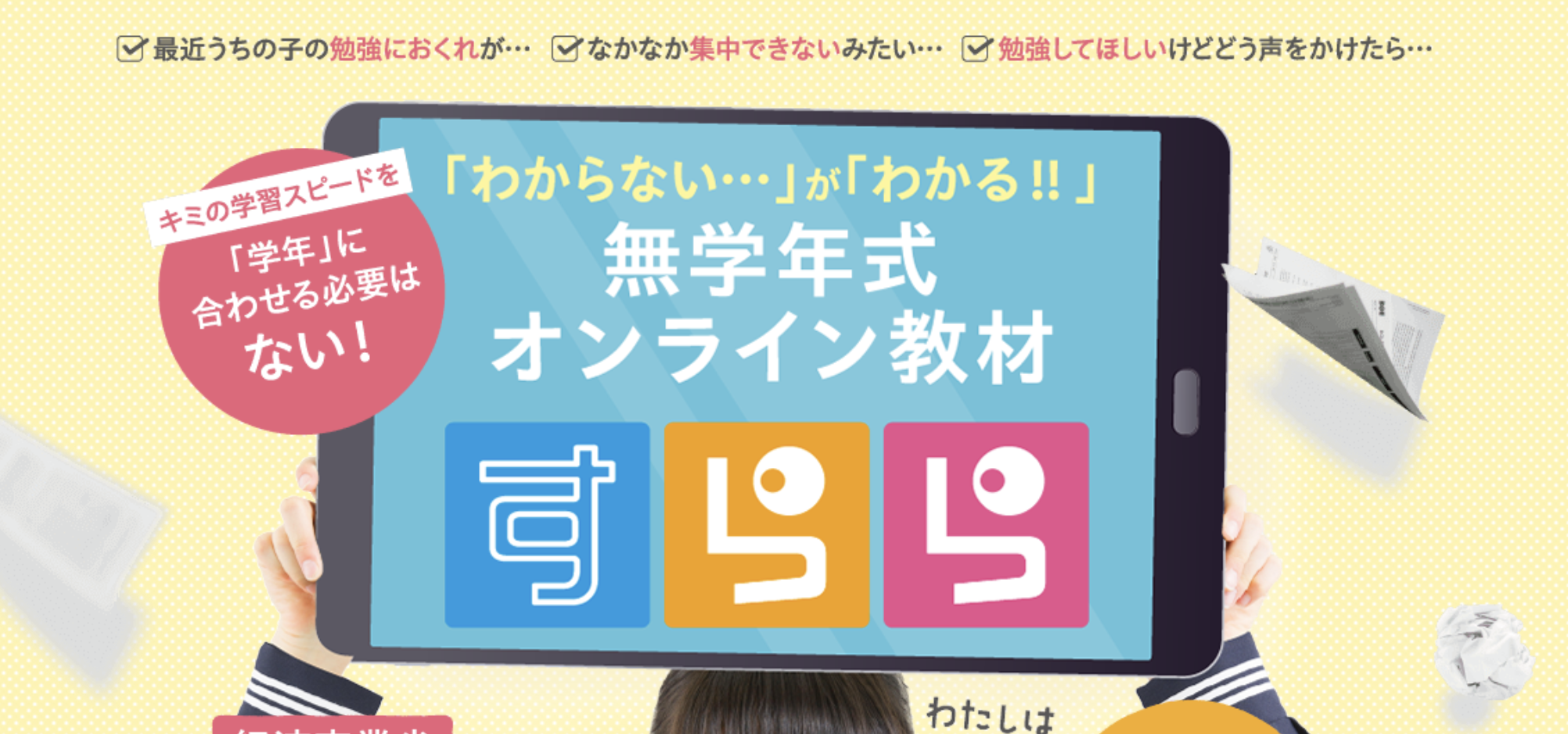すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
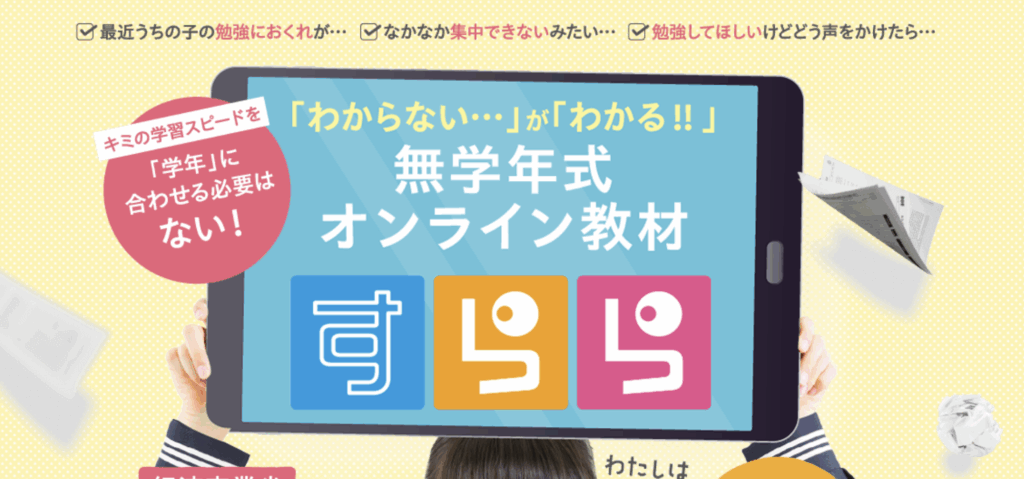
すららは、不登校の子どもたちが在宅学習を通じて学校の「出席扱い」を受けるための条件を満たしている家庭用タブレット教材です。
文部科学省のガイドラインでは、ICTを活用した自宅学習でも一定の要件を満たせば、出席として認められる可能性があるとされています。
すららは、その条件である「学習の質」「学習記録の提出」「学習の継続性」などに対応しており、実際に多くの保護者や学校から高い評価を得ています。
子どもが自分のペースで安心して学びながら、社会的な評価としての「出席」を得られる仕組みは、すららの大きな魅力の一つです。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららでは、日々の学習記録が自動的に蓄積され、保護者や学校が確認できる形式でデータ化されます。
これにより、学校側に提出できる「客観的な学習記録レポート」が簡単に用意できる点が強みです。
保護者が一からレポートを作成する必要がなく、システム上で確認された学習内容を元に、証明資料として出せるため、手間も少なくなります。
学習の質についても、単なる映像視聴や問題演習だけでなく、理解度を確認するステップや繰り返し学習が組み込まれているので、内容の信頼性も高く評価されます。
このような具体的な「証明力」があることで、すららは多くの学校で出席扱いとして認められやすくなっています。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららは自動で学習の履歴を保存してくれるため、提出用の学習記録レポートが簡単に出力できます。
学校側に対して「客観的な記録」を示すことができ、信頼性の高い証拠として活用できます。
日々の学習内容、時間、進捗度などが明確に分かるようになっており、出席扱いを希望する家庭にとって大きな安心材料となります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららでは、保護者が日々の学習管理を細かくチェックしなくても、システム上ですべての記録が残ります。
これにより、学習の様子が第三者(学校)にとっても一目で分かる「可視化された形」で確認できるのです。
このような客観的・継続的な証明が、出席扱いを判断する学校にとっても「安心材料」となりやすいのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
出席扱いを受ける際には、「学習が本人に合っており、継続されているか」が重要な判断基準になります。
すららでは、コーチが一人ひとりの状況に合わせて学習計画を作成し、継続できるよう定期的にサポートしてくれます。
ただ教材を与えるだけでなく、進捗のチェックや声かけ、モチベーション維持のための工夫が施されている点もポイントです。
このように、計画性と継続性の両面から学習をサポートする仕組みがあることで、学校側にも「学習している実態」がしっかり伝わります。
すららのこの支援体制は、不登校のお子様が学習習慣を維持しつつ、自信を取り戻すうえでも大きな助けとなっています。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららでは、専属のコーチが子どもの理解度や興味に応じた学習計画を立ててくれます。
その上で、学習が続けられるよう定期的にメッセージを送ったり、フォローを行ったりする仕組みも整っています。
こうした「計画性」と「継続性」の両方をアピールできることで、出席扱いを申請する際にも学校からの評価が得られやすくなっています。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららでは、子ども一人ひとりに合わせた学習計画を専任のコーチが作成してくれます。
この計画は、子どもの学習状況や性格、理解度などをもとにオーダーメイドで作られます。
また、単に計画を立てるだけでなく、継続的な進捗の確認や励ましのメッセージなど、伴走型のサポートも行われます。
家庭で孤立しがちな不登校の子どもにとって、外部からの定期的な声かけやフォローは学習へのモチベーション維持にもつながります。
こうした丁寧なサポート体制が、学習の継続性を保ち、出席扱いの条件にも合致する要素となります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは、学年にとらわれない「無学年式」の学習スタイルを採用しています。
そのため、学習の遅れがある子どもでも、自分のペースに合わせて基礎から丁寧に学び直すことができます。
また、得意な分野については学年を越えてどんどん進めることができるので、子どもが「自分で学べる」という実感を得やすくなります。
不登校の子どもによくある「前の単元が分からないから、今もつまずく」という悩みを根本から解消することが可能です。
こうした柔軟なカリキュラムは、学習内容の理解度向上だけでなく、学習そのものへの自信を育てる効果もあります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららでは、学習を家庭と子どもだけで完結させるのではなく、学校とも連携する体制を整えています。
家庭・学校・すららという三者が情報を共有し、連携を図ることで、よりスムーズに出席扱いの申請が進められる仕組みになっています。
保護者が一人で全ての手続きを行う負担が軽減されるだけでなく、学校側にも「きちんとした体制で学習を進めている」ことが伝わりやすくなります。
このような連携体制があることで、不登校の子どもが社会とつながる一歩を踏み出しやすくなるのも、すららの大きな魅力です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いの申請を行う際には、学習記録や活動報告書など、さまざまな書類の準備が必要になります。
すららでは、こうした書類について、保護者が迷わずに準備できるよう、詳細な案内やテンプレートを提供しています。
学校に何をどう説明すればよいのか分からないという家庭でも、すららのサポートがあれば安心して手続きを進められます。
初めて出席扱いを申請する方でも、手順に沿って準備ができるよう工夫されており、心強い存在となっています。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
出席扱いのためには、子どもの学習状況を学校に報告することが求められます。
すららでは、専任コーチがレポート提出用のフォーマットを提供し、書き方や内容のアドバイスも行ってくれます。
これにより、保護者が「何を書けばいいのか分からない」と悩むことがなくなり、スムーズな報告が可能になります。
また、コーチからのコメントが加わることで、より客観的な視点からの報告として信頼性が増します。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
保護者が学校の担任や校長と直接連絡を取るのは心理的にハードルが高いと感じることも少なくありません。
すららでは、出席扱いをスムーズに進めるために、学校との連携を取りやすくするサポートも行っています。
たとえば、事前にどのような説明をすればよいのか、どのタイミングで相談すべきかといった具体的なアドバイスがもらえます。
こうしたフォローがあることで、保護者も安心して学校側と話を進めることができ、出席扱いの申請が現実的に動き出しやすくなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が推奨する不登校対応教材として、多くの教育機関に認められています。
全国の教育委員会や学校との連携実績があり、実際に不登校の生徒がすららを通じて学び続けている事例も多くあります。
このような実績があることで、保護者はすららが信頼できる教材であることを実感しやすくなります。
また、すららが不登校支援教材として公式に利用されていることからも、その効果と信頼性は明確です。
教育機関からの認定を受けていることで、出席扱いの申請や学習進捗報告がよりスムーズに進みます。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会と協力し、不登校の子どもたちへの支援を行っています。
教育委員会と連携し、学校ごとのニーズに合わせた学習支援を提供しているため、各地域で高い信頼を得ています。
これにより、すららを利用する家庭も、学校や教育機関からの理解を得やすく、出席扱いの手続きが円滑に進むことが多いです。
すららの利用実績が広がることで、より多くの子どもたちが学び続けることができる環境が整えられています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、全国の教育機関から公式に「不登校支援教材」として認められています。
この公式認定は、すららが学習効果を証明し、教育現場でも信頼されていることの証です。
不登校の子どもたちに対しても、確かな学習の進行が保証されるため、保護者は安心して利用を続けることができます。
また、学校側でもすららを利用することで、学習進度を適切に把握でき、子どもが再登校した際にもスムーズに学習に復帰できるようサポートされています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っており、学校教育との一貫性を保つことができます。
学校のカリキュラムに基づいて学習することで、子どもたちは欠席していても、学校で学んでいる内容と同じものを学べる安心感があります。
これにより、すららの学習環境は、学校教育に準ずるものとして高く評価されやすくなります。
さらに、学習指導要領に沿った教材を提供することで、学校側もすららでの学習を出席扱いにしやすくなり、家庭にとっても負担が少なくなります。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららで提供される学習内容は、学校の学習指導要領に沿ったものです。
そのため、学年ごとに必要な知識やスキルをしっかりとカバーしており、学校での学習進度と一致します。
これにより、不登校の子どもも学校と同じペースで学習できるため、学力の低下を防ぎ、再登校した際にもスムーズに授業に復帰できます。
学習指導要領に沿っていることで、学校側の理解を得やすく、出席扱いにしてもらえるケースが増えます。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららは、学習の進捗や理解度をシステムでしっかりと評価し、フィードバックを提供しています。
定期的な進捗レポートが自動的に作成され、保護者や学校の先生が確認することができます。
これにより、学習の成果を客観的に評価でき、学校でもすららでの学習状況が把握しやすくなります。
フィードバックが定期的に行われることで、学習のモチベーションも維持しやすく、学び続ける力を育てることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは、不登校の子どもが学習を続けながら出席扱いとして認められる制度を提供しています。
この出席扱いを得るためには、いくつかの申請方法と必要書類が存在します。
以下では、出席扱いになるための具体的な申請方法について詳しく解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に、担任の先生や学校に相談することが重要です。
学校には、出席扱いの申請に関するルールや手続きがあり、各学校で異なる場合があります。
担任の先生とコミュニケーションをとることで、必要な書類や手続きについて具体的に確認することができます。
相談の際には、すららの利用状況や学習の進捗についても共有し、学習継続の意欲や目的を説明することが大切です。
学校側が出席扱いを認めるためには、学習の継続性と効果を証明する必要があります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、学校側が求める書類や条件を満たす必要があります。
一般的に、学習状況を示す証拠や進捗報告書が求められる場合があります。
すららでは、学習進捗や達成度を自動的にレポートとして出力する機能があり、これを学校に提出することで学習の継続性を証明できます。
学校によって求められる書類は異なるため、事前に確認し、必要な書類を整えておくことが重要です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。
特に、精神的な健康問題や発達障害、その他の病気が原因で不登校になっている場合、医師の意見が重要となります。
診断書や意見書には、子どもの不登校の状態とともに、「学習継続が望ましい旨」の記載が必要です。
これにより、学校側は不登校の理由を理解し、適切な支援を行いやすくなります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の理由によっては、診断書が必要となる場合があります。
精神的な不調や発達障害など、医学的な背景がある場合は、診断書を提出することで学校側に理解を得やすくなります。
診断書には、医師が子どもの状態を評価し、学習を続けることが重要であると記載される必要があります。
診断書があることで、学校側も出席扱いを認めやすくなり、適切なサポートが提供される可能性が高くなります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書は、精神科、心療内科、小児科など、専門の医師に依頼することができます。
診断書には、「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」が記載されることが求められます。
これにより、学校が出席扱いを認める際の根拠が明確になり、スムーズに手続きを進めることができます。
医師による適切な診断書は、保護者にとっても安心材料となり、学校との連携がより円滑になります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららの学習記録は、学習進捗や達成度が詳細に記録されています。
これらの学習記録を学校に提出することで、学習の継続性や進捗状況を証明することができます。
学校側にとっては、学習の結果や進捗が目に見える形で示されるため、出席扱いの申請をスムーズに進めるための重要な証拠となります。
進捗レポートをダウンロードし、担任や校長先生に提出することで、学校側が申請内容を確認しやすくなります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのプラットフォームでは、学習進捗に関する詳細なレポートをダウンロードすることができます。
このレポートには、子どもの学習時間や達成した内容、得られた成果が記録されており、学校に提出することで学習の証明として使用できます。
担任や校長先生に提出することで、学習の進捗がどのようになっているかを正確に示すことができ、出席扱いの判断を後押しする材料となります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学校側には出席扱い申請書の作成を求められることがあります。
この申請書は、保護者がサポートしながら学校と連携して作成します。
すららの学習記録を参考に、出席扱いを希望する理由を明確に記載することで、学校に提出する書類としての信頼性が高まります。
申請書を作成する過程で、保護者と学校が協力し、スムーズに手続きを進めることができます。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いを受けるためには、学校の承認と教育委員会の承認が必要です。
申請書や学習記録を提出した後、学校長の承認を得ることで、出席扱いの決定が下されます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校と連携し、必要書類を整えて申請を行います。
申請の承認を受けることができれば、出席扱いとして認められ、学習が正式に継続されることが確定します。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
学校長の承認が得られた時点で、出席扱いが正式に決まります。
学校側は学習記録や進捗レポートを元に、出席扱いを認めるかどうかを判断します。
出席扱いが認められることで、子どもが学んでいる証拠として学校の記録に残り、正式に出席として扱われることになります。
学校長の承認は、出席扱いの決定において最も重要なステップとなります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
教育委員会に申請が必要な場合は、学校と連携して申請を行います。
この場合、学校が申請書類を準備し、教育委員会に提出することになります。
教育委員会は、出席扱いの条件や学習継続の証明を基に判断を行います。
学校側と連携しながら進めることで、手続きが円滑に進み、承認を受けることが可能になります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子どもにとって、出席扱いが認められることは非常に重要なポイントです。
出席日数が足りなくなると、内申点の低下や進学に影響が出る可能性があります。
しかし、すららのようなオンライン学習サービスを活用することで、出席扱いとしてカウントされ、学業における評価を守ることができます。
ここでは、出席扱いを認めてもらうことで得られるメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校の場合、出席日数が足りないことで内申点が下がりやすくなりますが、出席扱いを受けることで、この問題を回避することができます。
すららを利用して学習を続けることで、学校側に出席日数としてカウントされるため、内申点の評価が悪化することなく、安定した学業成績を保つことができます。
学習を進める中で、教科ごとの理解度が高まるため、出席扱いが認められた場合、内申点を維持するために重要な要素となります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
出席扱いを受けることで、実際の出席日数がカウントされるため、欠席が原因で内申点が下がることがなくなります。
不登校の子どもにとって、出席日数がカウントされることは、内申点に大きな影響を与えるため、学業成績における評価を確保するための大きなメリットです。
学校が出席扱いとして認めることで、実際に授業を受けていないとみなされることなく、学業の成果が正当評価されます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いを受けることができると、進学における選択肢が広がります。
特に中学や高校進学の際に、出席扱いを受けていないと、進学の際に不利になる可能性がありますが、出席扱いが認められると、その心配が軽減されます。
進学先の選択肢が増えることで、将来の進路選択にもプラスの影響を与え、より多くの学校やコースにアクセスすることが可能となります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の子どもやその保護者にとって、「遅れている」「取り戻せない」という不安は大きなストレスになります。
すららを利用して学習を進めることで、授業の進度や内容に遅れを感じることなく、計画的に学習を進めることができます。
無学年式のカリキュラムと柔軟な学習ペースで、個別に学びの遅れを取り戻すことができ、子ども自身も安心して学習に取り組むことができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららでは、子どもの学習状況に合わせて、ペースを調整することができるため、学校の授業に遅れを感じることがなくなります。
自分のペースで学習を続けることができるので、他の子どもたちと比較して焦ることなく、着実に学習を進めることが可能です。
このように、学習が進むことで、授業の遅れを気にする必要がなくなり、精神的な負担も軽減されます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
学習環境が整うことで、子どもは自己肯定感を保ちながら学習に取り組むことができます。
遅れを気にすることなく、適切なサポートを受けながら進んでいけるので、子ども自身も自分に自信を持てるようになります。
すららのコーチングや学習サポートを通じて、子どもはポジティブな学習体験を重ね、自己肯定感を高めることができるのです。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ親にとって、心の負担はとても大きいものです。
特に、子どもが学習面で遅れを感じたり、将来の進学に不安を抱えていると、親としては何とか支えたいと感じることが多いでしょう。
すららを活用することで、学校、家庭、そしてすららコーチとの連携ができ、支援体制が整います。
これにより、親は一人で悩みや不安を抱えることなく、専門的なサポートを受けながら子どもの学習支援に取り組むことができます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、学校と家庭、そしてすららのコーチが連携して支援を行います。
これにより、親はすべてを一人で対応することなく、学校側とも情報共有をしながら子どもをサポートできるようになります。
家庭と学校、すららコーチの協力体制が整うことで、親は精神的にも安心感を持ち、子どもをしっかりと支えることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校でも出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの注意点があります。
すららを利用する際に、学校としっかりと連携を取り、出席扱いを認めてもらえるようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを利用して不登校の子どもが出席扱いになるためには、学校側の理解と協力が不可欠です。
学校によっては、出席扱いにすることに対して慎重な場合もありますので、学校との話し合いを慎重に進めることが重要です。
まず最初に、すららが「文部科学省のガイドラインに基づいた教材」であることを、学校側にしっかりと説明する必要があります。
この説明を通じて、すららが教育的に有効であることを理解してもらい、出席扱いを認めてもらいやすくするための第一歩を踏み出すことができます。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、全国の教育機関と連携し、文部科学省のガイドラインに準じて提供されている教育教材です。
そのため、教育機関にとっても信頼のおける教材であり、正式に学習の支援を行うための有効な手段となります。
学校側にその点を説明し、すららの教材が教育としてしっかりとした基準を満たしていることを伝えることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
すららの利用が出席扱いとして認められるためには、学校側の理解を得るための準備が必要です。
その際、すららの公式資料やガイドラインを持参することで、具体的な情報を提供し、学校側に安心感を与えることができます。
また、担任だけでなく、教頭や校長にも早めに相談しておくことが有効です。
学校側全体の理解を得ることで、スムーズに対応してもらえる可能性が高くなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書が必要になることがあります。
特に「体調不良」や「精神的な理由」が原因で不登校となっている場合、学校側から診断書を求められることが多いです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
不登校の原因が体調や精神的な理由である場合、学校側はその状態を把握し、適切な対応をするために医師の診断書を求めることがあります。
診断書を通じて、出席扱いとして認められるかどうかを学校側が判断するため、必要に応じて医師に相談することが求められます。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書が必要な場合、まずは通院している小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝えましょう。
医師には、出席扱いを申請するために必要な診断書を求めていることを伝え、適切な対応をしてもらうことが大切です。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書を依頼する際、家庭での学習状況やお子さんの学習に対する意欲を具体的に説明することが大切です。
医師に前向きな記載をお願いすることで、出席扱いを認めてもらう際に有利になることがあります。
また、医師にとっても、お子さんの状況を詳しく伝えることで、適切な診断書を作成しやすくなります。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを認めてもらうためには、学習時間や内容が学校の授業に準じた水準である必要があります。
単に自分で勉強するだけではなく、授業に合わせた内容で学習を進めることが求められます。
すららは、学校のカリキュラムに基づいた内容を提供しており、出席扱いの申請においても有利に働くポイントとなります。
これにより、学習が学校の学びに近い形で行われていることが証明でき、教育委員会や学校側からも受け入れられやすくなります。
また、出席扱いを申請する際に、学習内容が「自習」や「自由学習」とは異なる、規定の教材やカリキュラムに基づいていることが強調されます。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
出席扱いを認めてもらうためには、ただ単に自由に学習しているだけではなく、学習内容が学校での授業に準じていることが重要です。
これが求められる理由は、出席扱いを許可するために必要な条件として、家庭学習が学校教育の一部として評価される必要があるためです。
すららでは、学校のカリキュラムに準じた内容の教材が提供されるため、この点で安心して学習を進められます。
自宅学習が学校の教育内容と一致していることを証明するために、学習内容や進捗をきちんと記録できる点も、出席扱いを申請する際に大きなポイントとなります。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間についても学校の授業時間を意識することが大切です。
出席扱いを認めてもらうためには、学習のボリュームが学校での授業に見合った内容である必要があり、目安としては1日2〜3時間程度の学習時間が推奨されます。
これにより、家庭学習が学校の授業時間と同等に評価されるようになり、出席扱いとして認められる確率が高くなります。
すららは、時間管理をサポートする機能もあり、学習の進捗や時間をしっかりと記録できるので、出席扱い申請時に学校に提出する際に役立ちます。
学習時間が不足していると評価されることなく、安定して学校の指導に準じた学習時間を確保することができます。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
学習内容については、主要教科だけではなく全教科をバランスよく学習することが求められます。
これは、学校での授業内容が全教科にわたって進められているため、出席扱いとして認めてもらうためには、主要教科に偏った学習だけでは不十分だとされるためです。
すららは、国語、算数、理科、社会などの全教科に対応した教材を提供しています。
全教科を学ぶことで、学校のカリキュラムに沿った学びを進めることができ、出席扱いとしての条件を満たすことができます。
このように、すららを使った学習は、学校での教育をしっかりとカバーするものとみなされやすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いを認めてもらうためには、学校と家庭で学習状況を共有することが条件となることが多いです。
このため、学校との定期的なコミュニケーションが非常に重要です。
学習状況をしっかりと伝えることで、出席扱いとしての認定を受けやすくなります。
例えば、すららで学習した進捗や成果を定期的に報告することが求められます。
月に1回は学習レポートを提出することが推奨されており、これはすららのシステムから簡単にダウンロードできます。
このレポートを担任や校長に提出することで、家庭での学習状況が学校側に伝わり、出席扱いを認めてもらうための手続きが円滑に進みます。
また、学校から求められた場合には家庭訪問や面談に対応することも必要です。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗状況を共有することが望ましく、積極的にコミュニケーションを取ることで、信頼関係を築くことが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
出席扱いを認めてもらうためには、学校と家庭で学習状況を共有することが大切です。
この共有は、学校側が生徒の学習進捗を把握し、家庭と連携して支援を行うための基盤となります。
「学習が進んでいる」と確認できることで、学校側は不登校の生徒を支援しやすくなります。
家庭での学習状況や進捗を学校と定期的に共有することが、出席扱いを得るための条件の一つと言えます。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
出席扱いを申請する際には、学習レポートを月に1回提出することが推奨されています。
この学習レポートは、すららのシステムから簡単にダウンロードできます。
レポートには、生徒の学習進捗や成果が記録されており、学校側に提出することで、学習の状況が確認されます。
これにより、学習が順調に進んでいることを証明でき、出席扱いの認定を受けやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
出席扱いを申請する際、学校側から家庭訪問や面談を求められる場合があります。
この際、学校側は学習状況や家庭での取り組みをより詳しく確認したいと考えています。
家庭訪問や面談に対応することで、学校と協力して学習を進めていることをアピールできます。
これにより、出席扱いの認定を受けるための一助となります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生とは、こまめにメールや電話で学習進捗を共有することが推奨されます。
定期的な連絡を通じて、学校側が生徒の学習状況を把握しやすくなります。
これにより、担任の先生も生徒に対してより適切なサポートを行いやすくなります。
こまめな連絡で、学校と家庭の協力体制を強化し、出席扱いの認定に向けて進めることができます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
教育委員会への申請が必要な場合もあります。
これは、学校での出席扱いが認められた後、さらに教育委員会の承認を得る必要がある場合に発生します。
そのため、教育委員会向けの資料準備も重要なステップです。
資料の準備は、学校と相談しながら進めることが推奨されます。
学校と連携を取りながら進めることで、教育委員会に提出する際に必要な書類や情報が整っているか確認できます。
教育委員会に提出する資料が整うことで、正式に出席扱いとして認められる可能性が高まります。
こうした手続きをスムーズに進めるためには、学校との密な連携が非常に重要です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会向けの資料準備は、学校と連携して進めることが重要です。
出席扱いを認めてもらうためには、学校と協力して必要な資料や証拠を整える必要があります。
学校側の理解を得ることが、教育委員会に対してスムーズに申請できる第一歩です。
このため、学校と連携を取りながら、資料準備を進めていくことが求められます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
不登校の子どもが「すらら」を使用する場合、出席扱いを認めてもらうためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、学校に出席扱いを認めてもらうための成功ポイントをいくつか紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介することは非常に効果的です。
学校側は他校の成功事例を参考にすることで、実施に対する不安を減らしやすくなります。
事例を共有することで、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高くなります。
他校での成功事例を提示することは、学校にとって安心材料となり、申請の承認を得やすくする手段になります。
実際に他校で出席扱いが認められた事例があることを学校に伝えることで、学校の担当者が積極的に対応してくれる可能性が高まります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介することは、非常に効果的です。
学校側は他校の事例を参考にすることで、実施する際の不安を軽減しやすくなります。
事例を共有することで、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高くなります。
実際に他校で成功していることが確認できると、学校側も安心して申請を進めることができます。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには、出席扱いに関する実績紹介が掲載されています。
この実績紹介をプリントして持参することが、学校側に対して信頼を与える方法です。
実績を見せることで、学校はすららの信頼性を確認でき、出席扱いの申請を前向きに検討する可能性が高まります。
プリントした資料を持参することで、具体的な証拠を提示することができ、申請が認められる可能性が増します。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
「本人のやる気」を学校にアピールすることは、出席扱いを認めてもらうために非常に重要です。
本人がどれだけ前向きに学習に取り組んでいるかを示すことが、学校側の理解を得るための大きな要素となります。
一つの方法として、本人が学習を通じて感じたことや目標を書いた感想を提出することが挙げられます。
これによって、学校側に対して学習に対する本気度や意欲を伝えることができます。
また、面談がある場合には、本人自身も参加して「頑張っている」と直接伝えると効果的です。
面談時に自分の努力を話すことは、学校側に本人がどれだけ学びたいと思っているのかを伝える大きなチャンスです。
積極的に学習している姿勢を見せることで、出席扱いを認めてもらえる可能性が高まります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
本人が学習を通してどのような感想を持ち、今後どんな目標を持っているかを具体的に記した感想文や目標設定の提出は、出席扱いを認めてもらうために重要です。
これにより、学校側は本人の学習への意欲を確認することができます。
また、この方法は、学校の先生に対して「自分の意思で学んでいる」というアピールを行うことにも繋がります。
感想や目標は具体的であればあるほど、学校側に良い印象を与えます。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校側との面談において、本人も積極的に参加し、自分の努力を直接伝えることは非常に効果的です。
親だけでなく、本人が積極的に関わる姿勢を見せることで、学校側もその努力を評価しやすくなります。
面談時に自分の努力を話すことは、学校側に本人がどれだけ学びたいと思っているのかを伝える大きなチャンスです。
積極的に学習している姿勢を見せることで、出席扱いを認めてもらえる可能性が高まります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
「無理なく、継続可能な学習計画」を立てることは、出席扱いを認めてもらうために非常に大切なポイントです。
継続的な学習が最も重要であり、そのためには本人に合った現実的な学習計画が欠かせません。
すららを使用する場合、本人のペースに合わせて学習を進めることが可能です。
しかし、その際に無理なスケジュールを組んでしまうと、学習が続かなくなり、最終的には学習が途切れてしまう可能性もあります。
本人が続けられるペースを意識し、無理のない計画を立てることが、出席扱いの認定を受けるためにも重要です。
すららのコーチに相談しながら、現実的なスケジュールを一緒に作成することをお勧めします。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習の継続が最も大事なため、計画を立てる際には、本人の体調や精神的な状態に合わせたペースで学習を進めることが必要です。
無理に進めると逆効果になることもあります。
すららを使用する場合、オンラインで自分のペースで学習できるため、負担が少なく続けやすい環境が整っています。
そのため、本人に合ったペースで学習できる計画を立てることが成功の鍵となります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
学習計画を立てる際には、すららのコーチに相談し、現実的なスケジュールを一緒に作成してもらうと良いでしょう。
コーチは、進行具合を見ながら、本人に適した学習計画を提案してくれます。
コーチのサポートを受けることで、学習の進捗に応じて柔軟に計画を変更したり、モチベーションを維持するための工夫をすることができます。
このようなサポートを受けることが、継続的な学習を可能にします。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
「すららコーチ」をフル活用することは、出席扱いを認めてもらうために非常に効果的です。
コーチは、学習計画のサポートだけでなく、学習の進捗状況をレポートとしてまとめたり、学校に提出する証明を作成する手助けをしてくれます。
すららコーチは、学習状況を常に把握しており、適切なフィードバックを提供することができます。
これにより、学校側に対しても継続的な学習を証明することができ、出席扱いを受けるための材料となります。
コーチをフル活用することで、学習の進捗や成果をしっかりと記録に残すことができ、学校側にも確かな証拠を提供することができます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
出席扱いを申請するためには、学習の証明となるレポートや証明書が必要となることがあります。
すららコーチは、この部分もサポートしてくれるので安心です。
コーチは、学習の進捗を記録し、定期的に学校に提出するためのレポートを作成してくれます。
これにより、学校側にも継続的に学習していることを示す証拠となり、出席扱いを受けるための強い後押しとなります。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた!時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
「すらら」を利用する際に、よくある質問や疑問を解消するためのQ&Aをまとめました。
「すらら」が不登校の子どもにどのように対応するか、また発達障害に関するコースや料金プランについてなど、多くの方が気になるポイントについて詳しく説明します。
これらの質問を参考にして、すららの利用に関する疑問を解消してください。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら」に関する口コミで「うざい」という意見が時折見受けられますが、なぜそのような意見が出ているのでしょうか?
一部の利用者は、すららの学習進捗を追跡するための通知が頻繁に送られてくる点や、繰り返しの指導に対して「うざい」と感じることがあるようです。
また、課題に対するフィードバックが多すぎると感じることもあるかもしれません。
ですが、これは一方で学習の効果を上げるために重要なポイントでもあります。
ただし、このような「うざい」と感じる部分に関しては、ユーザーが設定を調整することである程度改善可能です。
ユーザーが自分のペースで学べるよう、学習プランをカスタマイズできる点もあります。
この点を理解して、上手に利用することで「うざい」と感じずにすららを使うことができます。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには発達障害に特化した学習プランが用意されており、料金プランも特別な設定があります。
発達障害コースでは、通常の学習プランよりも個別のサポートが強化されており、特別支援が必要な場合には、より手厚い支援が行われます。
このコースの料金は、通常プランよりやや高めに設定されていることが多いですが、その分、専門的なサポートが提供されるため、効果的に学習を進めることができます。
また、発達障害コースでは個別に学習進捗を確認し、必要に応じてペースを調整するため、学習が継続しやすい環境が整っています。
詳しい料金については公式サイトで確認することができますが、各プランに応じてさまざまなオプションが用意されているので、自分のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららのタブレット学習は、不登校の子どもにとって非常に有益な学習方法となります。
不登校の子どもがすららを使用することで、学習内容を自分のペースで進められるため、精神的な負担を減らしながら学習を続けることができます。
また、すららでの学習が出席扱いとして認められる場合もあります。
学校により異なる場合がありますが、学習の進捗状況や成果を証明できるレポートを提出することで、出席扱いとして認められることが多いです。
したがって、すららを活用して学習を続けることが、出席扱いを得るためのポイントとなります。
詳しい情報は、学校や教育委員会に確認しておくと良いでしょう。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは定期的にキャンペーンを実施しており、その際に提供されるキャンペーンコードを使用することで、料金の割引や特典を受けることができます。
キャンペーンコードの使い方は非常に簡単です。
すららの公式サイトで、申し込みの際に「キャンペーンコード」の欄にコードを入力するだけで、割引や特典が自動的に適用されます。
なお、キャンペーンコードには有効期限が設定されていることが多いため、使用する前に必ず有効期限を確認しておくことをお勧めします。
また、特定の条件を満たすことで割引が適用されるキャンペーンもあるため、詳細はキャンペーンページで確認しておきましょう。
すららをお得に利用できるチャンスなので、キャンペーンコードを活用することをお勧めします。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
「すらら」を退会する場合、公式サイトから手続きを行うことができます。
退会手続きは簡単で、ユーザーアカウントにログイン後、設定メニューから退会の手続きを選ぶだけです。
ただし、退会を希望する場合は、月額料金が支払われている場合でも、次回の更新前に手続きを完了する必要があります。
また、退会後はすららのサービスを再度利用することができないため、必要な場合は再登録が必要です。
退会手続きに関する詳細は、公式サイトに記載されていますので、退会前に確認しておくとスムーズに進めることができます。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
「すらら」の学習プランでは、基本的に入会金と毎月の受講料が主な料金です。
受講料には、全ての教材やサポートが含まれていますので、基本的には追加料金は発生しません。
しかし、特定のオプションやアドオン(例えば、特別なコーチングや個別指導)の利用時には追加料金が発生することがあります。
また、イベントや特別なキャンペーンに参加する場合も、追加の料金がかかることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
すららの料金体系はシンプルで分かりやすいため、料金に関する心配は少ないです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららのサービスは、基本的に1アカウントに対して1名の受講が想定されています。
そのため、兄弟姉妹が一緒に利用する場合、基本的にはそれぞれのアカウントを作成し、受講料を支払う必要があります。
ただし、特定のキャンペーンやオプションによっては、兄弟姉妹での共有利用が可能となることもあります。
その場合、割引や特別プランが提供されることもあるため、公式サイトやサポートに問い合わせて確認すると良いでしょう。
受講料については、兄弟で使う場合の割引や特典についてもチェックしてみてください。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、英語の学習内容も含まれています。
特に、英語に関しては、基礎的な学習から始まり、聞く・話す・読む・書くといったスキルを身につけることができる内容になっています。
コースの内容には、英語の単語やフレーズを学ぶことができるコンテンツも豊富にあり、子どもが楽しく学べるように工夫されています。
また、すららの英語学習は、進捗に合わせた個別学習が可能なため、自分のペースでじっくり学べます。
英語学習を積極的に取り入れたい場合は、小学生コースを選ぶことで、しっかりとした基礎固めができるでしょう。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチは、学習に関するサポートを個別に提供してくれます。
コーチは、学習の進捗状況をモニタリングし、必要に応じてアドバイスやフィードバックを行います。
また、学習の内容に関して不明点や困ったことがあれば、コーチから直接サポートを受けることができます。
特に、難しい課題に直面した場合やモチベーションが下がってしまった場合、コーチは適切なタイミングでサポートを提供し、前向きな学習環境を作り出します。
このように、すららのコーチは学習に対して心強いサポート役となり、より効果的な学びを実現します。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
「すらら」は、不登校の子供たちにも対応できる学習プログラムを提供しており、家庭での学習を支援します。
しかし、出席扱いとして認められるかどうかは学校の方針や状況に依存します。
今回は、すららがどのように不登校の子供たちに役立つのか、また他の家庭用タブレット教材と比較してどのようなメリットや特徴があるのかを詳しく解説します。
不登校の子供が学びながら安心して学習を続けるためには、柔軟で適切な教材の選定が重要です。
すららの特徴や他の教材との違いを理解することで、より効果的な学習の方法を見つけられるでしょう。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
「すらら」は、不登校の子供たちに自宅で学習を続けるための強力なサポートを提供するタブレット教材です。
出席扱いにするためには、学校との協力が不可欠であり、学習内容や学習時間を学校の基準に合わせることが求められます。
具体的な手順としては、学校側への説明、医師の診断書、学習レポートの提出などが必要です。
申請が成功するためには、子供のやる気や学習計画の実現可能性を学校にしっかり伝えることが重要です。
学校との定期的なコミュニケーションや、すららコーチのサポートを積極的に活用することが、出席扱いを認めてもらうポイントとなります。
本記事を参考にして、しっかりと準備を整え、安心して学習を進められる環境を作りましょう。